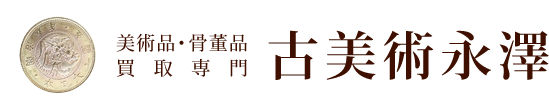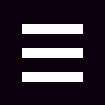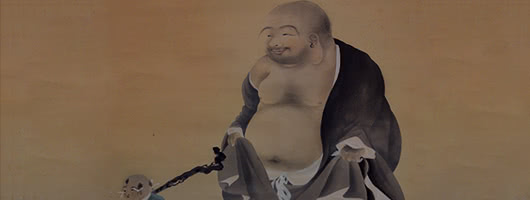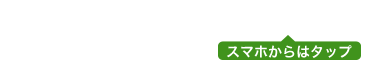野田弘志
のだ ひろし
野田弘志 について
野田弘志の作品を高く評価しております。
もし作品がお手元にございましたらぜひご相談ください。
野田弘志(のだ ひろし、1936年-)は昭和から平成時代に活躍する日本の画家である。
1936年6月11日に戦時中であったため、韓国全羅南道で生まれる(本籍地は広島県沼隈郡柳津村)。幼少期を中国で過ごし、終戦の年に両親とともに帰国して広島や静岡で暮らし、中学・高校時代を豊橋市で過ごした。中学・高校時代にデッサンや油彩画をよく描くようになり、画技を磨くため上京。
上京後は阿佐ヶ谷美術学園洋画研究所に通うかたわら、洋画家・森清治郎について指導を受けるなど本格的に油彩画に取り組む。翌年には東京芸術大学に入学。在学中に白日会へ出品・受賞し、洋画家としての頭角をあらわす。同校卒業後は画家ではなく、イラストレーターとして東急エージェンシーに入社。そのかたわら、白日展、安井賞展などで作品の発表を続ける。
1970年から制作活動に専念。作品の傾向は、黒い背景によって特徴づけられる絵画であり、壁も境目もない空間に果実や鉱物が浮遊するかのようにあらわされるが、物質そのものを現実から引き離すことによって、その存在感や質感を強く引き出される。「やませみ」 (1971年) や「黒い風景 其の参」(1973年) はこの時代の作品である。黒い背景といっても一様に同じ色ではなく、肌理の目立ったものや、雲を描いたもの、素材に変化を持たせて光沢を大胆に変化させ対比させたものなどがあり、多様性に富んでいる。この黒の時代は1970年代で終わりを告げる。
1980年代になると金箔を背景とした華やかな作品が描かれる。この時期の特徴は、金箔による黄金背景や、黄赤系統の絵具による一面を覆う黄金色の物体の表現はである。
1983年から朝日新聞連載小説・加賀乙彦作『湿原』の挿絵の原画を鉛筆を用いて制作する。その入念で細密な完成度の高い鉛筆画は、高く評価され注目を集める。
1990年代以降の代表的な作品群は、白や灰色を基調色とする壮大な連作である。21世紀に入ってからは明るい灰色の作品が多くなっている。同時期の、小品では暗い灰色も多用されている。絢爛な色彩の薔薇の作品も多数描かれている。
1991年には画家に時間の集積と生命の形相を意識させる骨を中心とし、広い空間を扱った大画面が特徴的な、一段と意識の高い作品群であるTOKIJIKU(非時)という連作が開始された。
また、日本だけでなく、1990年にベルギーで個展を開催するなど活躍している。
三島由紀夫、加賀乙彦、宮尾登美子の小説の挿画を担当した事でも有名である。
年表
1936年 韓国に生まれる
1945年 帰国
1951年 静岡県に転居
1956年 上京して阿佐ヶ谷美術学園洋画研究所に通う
1957年 東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻に入学
1960年 白日会第36回展に初入選・受賞
1961年 東急エージェンシー企画調査部制作課に入社
1962年 白日会会員となる
東急エージェンシーを退社 独立する
1966年 三島由紀夫の挿画を担当
1970年 初個展を開催
1974年 東京造形大学非常勤講師となる
1983年 白日会第58回展で内閣総理大臣賞を受賞
加賀乙彦の挿画を担当
1987年 白日会常任理事となる
加賀乙彦・宮尾登美子の挿画を担当
1988年 第3回具象絵画ビエンナーレ 出品
1990年 ベルギーで個展を開催
1992年 多数の展覧会に出品
1994年 第12回宮本三郎記念賞 受賞
2007年 大規模な回顧展を開催
1936年6月11日に戦時中であったため、韓国全羅南道で生まれる(本籍地は広島県沼隈郡柳津村)。幼少期を中国で過ごし、終戦の年に両親とともに帰国して広島や静岡で暮らし、中学・高校時代を豊橋市で過ごした。中学・高校時代にデッサンや油彩画をよく描くようになり、画技を磨くため上京。
上京後は阿佐ヶ谷美術学園洋画研究所に通うかたわら、洋画家・森清治郎について指導を受けるなど本格的に油彩画に取り組む。翌年には東京芸術大学に入学。在学中に白日会へ出品・受賞し、洋画家としての頭角をあらわす。同校卒業後は画家ではなく、イラストレーターとして東急エージェンシーに入社。そのかたわら、白日展、安井賞展などで作品の発表を続ける。
1970年から制作活動に専念。作品の傾向は、黒い背景によって特徴づけられる絵画であり、壁も境目もない空間に果実や鉱物が浮遊するかのようにあらわされるが、物質そのものを現実から引き離すことによって、その存在感や質感を強く引き出される。「やませみ」 (1971年) や「黒い風景 其の参」(1973年) はこの時代の作品である。黒い背景といっても一様に同じ色ではなく、肌理の目立ったものや、雲を描いたもの、素材に変化を持たせて光沢を大胆に変化させ対比させたものなどがあり、多様性に富んでいる。この黒の時代は1970年代で終わりを告げる。
1980年代になると金箔を背景とした華やかな作品が描かれる。この時期の特徴は、金箔による黄金背景や、黄赤系統の絵具による一面を覆う黄金色の物体の表現はである。
1983年から朝日新聞連載小説・加賀乙彦作『湿原』の挿絵の原画を鉛筆を用いて制作する。その入念で細密な完成度の高い鉛筆画は、高く評価され注目を集める。
1990年代以降の代表的な作品群は、白や灰色を基調色とする壮大な連作である。21世紀に入ってからは明るい灰色の作品が多くなっている。同時期の、小品では暗い灰色も多用されている。絢爛な色彩の薔薇の作品も多数描かれている。
1991年には画家に時間の集積と生命の形相を意識させる骨を中心とし、広い空間を扱った大画面が特徴的な、一段と意識の高い作品群であるTOKIJIKU(非時)という連作が開始された。
また、日本だけでなく、1990年にベルギーで個展を開催するなど活躍している。
三島由紀夫、加賀乙彦、宮尾登美子の小説の挿画を担当した事でも有名である。
年表
1936年 韓国に生まれる
1945年 帰国
1951年 静岡県に転居
1956年 上京して阿佐ヶ谷美術学園洋画研究所に通う
1957年 東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻に入学
1960年 白日会第36回展に初入選・受賞
1961年 東急エージェンシー企画調査部制作課に入社
1962年 白日会会員となる
東急エージェンシーを退社 独立する
1966年 三島由紀夫の挿画を担当
1970年 初個展を開催
1974年 東京造形大学非常勤講師となる
1983年 白日会第58回展で内閣総理大臣賞を受賞
加賀乙彦の挿画を担当
1987年 白日会常任理事となる
加賀乙彦・宮尾登美子の挿画を担当
1988年 第3回具象絵画ビエンナーレ 出品
1990年 ベルギーで個展を開催
1992年 多数の展覧会に出品
1994年 第12回宮本三郎記念賞 受賞
2007年 大規模な回顧展を開催
出張買取
Step1
出張依頼
お気軽にご相談ください。お電話・LINE・メールフォームから承ります。

Step2
日時決定
お品物についてお聞きした後、ご都合のよいご訪問日時を調整し決定いたします。

Step3
ご訪問・査定
ご指定の日時に目利きがご訪問し、お品物を拝見して、査定額をご提示いたします。

Step4
買取・お支払い
ご提示した査定額にご納得いただきましたら、その場で現金でお支払いいたします。

美術品の時価評価が必要な皆さまへ
野田弘志を含め、相続や企業の帳簿価格の見直し等で必要な美術品・骨董品の時価評価は、「美術品評価サービス」がございます。 美術品評価サービスについて