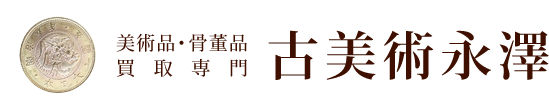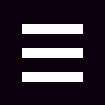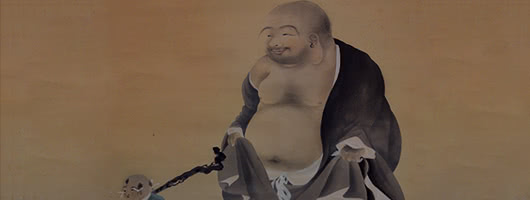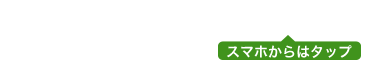徳川慶喜
とくがわ よしのぶ
徳川慶喜 について
徳川慶喜の作品を高く評価しております。
もし作品がお手元にございましたらぜひご相談ください。
徳川慶喜(とくがわ よしのぶ 1837年10月28日-1913年11月22日)は江戸幕府、日本史に残る最後の征夷大将軍。
水戸藩9代目当主、徳川斉昭の7男。
幼名は松平七郎麻呂。
斉昭の教育方針で9歳ごろまで水戸で過ごす。
この頃に弘道館で会沢正志斎らから学問や武術を教わる。
黒船来航の混乱時に家康が死去。跡継ぎの家定は病弱であったため、将軍跡継ぎ問題が勃発。
慶喜を推薦する斉昭や、薩摩藩主の島津斉彬ら一橋派、徳川慶福(のちの家茂)を推薦する彦根藩主、井伊直弼や、本寿院をはじめとする大奥の南紀派が対立。
島津斉彬の死後、一橋派は勢いをなくし、将軍は家茂となった。
大老となった井伊直弼が日米修好通商条約を調印させ、慶喜らは隠居謹慎処分を受ける。(安政の大獄)
1866年7月20日、家茂が死去。
家茂の後継ぎとして、老中から次期将軍に推薦されるも固辞。
8月20日に徳川家の家督は継いだもののはじめは将軍職に就くことを拒み続け12月5日にようやく就任した。
薩摩、長州が武力倒幕に傾倒することを予想し、1867年10月14日大政奉還を行い、明治天皇に政権を返上した。
戊辰戦争時、1868年1月に勃発した鳥羽・伏見の戦いで薩摩藩兵との武力衝突に至るも、自分が指揮する旧幕府軍に残るように指示し、勝つ余地があったのにもかかわず自分は側近などを連れて退却した。
その後、慶喜を朝敵とする命が下り駿河の宝台院に移り謹慎。
これによって事実上、徳川家の政権は幕を閉じた。
1869年、戊辰戦争の終結と共に謹慎が解除され、静岡に移り住む。
写真や狩猟など趣味に没頭し、巣鴨、文京区に移住し、77歳の頃、急性肺炎のため逝去。
水戸藩9代目当主、徳川斉昭の7男。
幼名は松平七郎麻呂。
斉昭の教育方針で9歳ごろまで水戸で過ごす。
この頃に弘道館で会沢正志斎らから学問や武術を教わる。
黒船来航の混乱時に家康が死去。跡継ぎの家定は病弱であったため、将軍跡継ぎ問題が勃発。
慶喜を推薦する斉昭や、薩摩藩主の島津斉彬ら一橋派、徳川慶福(のちの家茂)を推薦する彦根藩主、井伊直弼や、本寿院をはじめとする大奥の南紀派が対立。
島津斉彬の死後、一橋派は勢いをなくし、将軍は家茂となった。
大老となった井伊直弼が日米修好通商条約を調印させ、慶喜らは隠居謹慎処分を受ける。(安政の大獄)
1866年7月20日、家茂が死去。
家茂の後継ぎとして、老中から次期将軍に推薦されるも固辞。
8月20日に徳川家の家督は継いだもののはじめは将軍職に就くことを拒み続け12月5日にようやく就任した。
薩摩、長州が武力倒幕に傾倒することを予想し、1867年10月14日大政奉還を行い、明治天皇に政権を返上した。
戊辰戦争時、1868年1月に勃発した鳥羽・伏見の戦いで薩摩藩兵との武力衝突に至るも、自分が指揮する旧幕府軍に残るように指示し、勝つ余地があったのにもかかわず自分は側近などを連れて退却した。
その後、慶喜を朝敵とする命が下り駿河の宝台院に移り謹慎。
これによって事実上、徳川家の政権は幕を閉じた。
1869年、戊辰戦争の終結と共に謹慎が解除され、静岡に移り住む。
写真や狩猟など趣味に没頭し、巣鴨、文京区に移住し、77歳の頃、急性肺炎のため逝去。
徳川慶喜 の代表的な作品
- 「西洋風景」
出張買取
Step1
出張依頼
お気軽にご相談ください。お電話・LINE・メールフォームから承ります。

Step2
日時決定
お品物についてお聞きした後、ご都合のよいご訪問日時を調整し決定いたします。

Step3
ご訪問・査定
ご指定の日時に目利きがご訪問し、お品物を拝見して、査定額をご提示いたします。

Step4
買取・お支払い
ご提示した査定額にご納得いただきましたら、その場で現金でお支払いいたします。

美術品の時価評価が必要な皆さまへ
徳川慶喜を含め、相続や企業の帳簿価格の見直し等で必要な美術品・骨董品の時価評価は、「美術品評価サービス」がございます。 美術品評価サービスについて